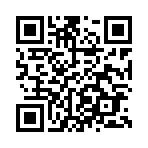2007年05月05日
ニモの行方を突き止めろ・・・という話
こんなニュース見つけちゃいました。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Friday, 4 May 2007 BBC News
サンゴ礁にすむある種の魚には帰巣本能があるということが分かったそうです。
対象になった熱帯魚は「ファインディング・ニモ」で有名になった orange
clownfish (オレンジクラウンフィッシュ)と vagabond butterflyfish (フウライチョウチョウウオ)の2種類でした。研究チームはこの2種類の魚の幼魚に目印をつけ、大海原で数週間から数ヶ月過ごして成長した魚がどこに行くのかをつきとめたのです。
オーストラリアはクイーンズランドにある James Cook University (ジェームスクック大学)の Geoff Jones 教授によると、サンゴ礁の魚はとても小さい卵を産み海に放出し、それらは小さな幼生になり時には何ヶ月も海流を漂っていると考えられているそうです。教授たちは常に幼生たちはどこへいくのか、という疑問を考え続けていたと言います。
しかし今までは調査をするのは容易ではありませんでした。そこで研究者達は国際チームを作り問題解決にあたります。彼らが目をつけたのは母親でした。彼らはパプアニューギニアの Kimbe Bay(キンベ湾)からメスの魚を集め barium isotope を注入しました。アイソトープは骨などに蓄積され子供に伝わります。
数週間後チームはサンゴ礁に戻り小さい魚を採集し彼らに「しるし」があるか調査したところ、60パーセントが元の場所に戻っていることが確認されたのです。これは予期せぬ結果だと教授は語っています。
この2種類の熱帯魚がどのように生まれ故郷に戻るのかはまだはっきりと分かっておらず、今後も研究を続けていきたいと研究者は語ります。おそらくはホームアイランドを感じる何らかの感覚があって自分達の位置を確認することができ遠くまで漂うことはないか、遠くまで流されても帰巣のメカニズムが働きもとの場所に泳いで戻ってくることができるのではないかと
Jones 教授は言います。
教授はこの発見は他の熱帯魚にも当てはまり、もしそうであれば魚の持ち出し禁止区域をつくることは、乱獲された魚を保護するために有効な方法ではないかと考えています。というのもそこには数を維持するのに十分な幼魚が戻ってくるはずだからと彼は言います。
◆◇◆
2003年に日本でも公開された映画「ファインディング・ニモ」のせいでカクレクマノミやナンヨウハギが乱獲されていると一時期話題になっていましたが今海の中はどうなっているのでしょうか。
一方岡山理科大専門学校でクマノミの大量養殖に成功し販売ルートに乗りつつあるというニュースもありますが・・・。
癒されるならニモグッズで

キュービーはカワイイ人気のキャラクターを四角いのミュージックロボット。顔を“パコパコ”さ...

3Pボーイズブリーフニモ4・6才
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Friday, 4 May 2007 BBC News
サンゴ礁にすむある種の魚には帰巣本能があるということが分かったそうです。
対象になった熱帯魚は「ファインディング・ニモ」で有名になった orange
clownfish (オレンジクラウンフィッシュ)と vagabond butterflyfish (フウライチョウチョウウオ)の2種類でした。研究チームはこの2種類の魚の幼魚に目印をつけ、大海原で数週間から数ヶ月過ごして成長した魚がどこに行くのかをつきとめたのです。
オーストラリアはクイーンズランドにある James Cook University (ジェームスクック大学)の Geoff Jones 教授によると、サンゴ礁の魚はとても小さい卵を産み海に放出し、それらは小さな幼生になり時には何ヶ月も海流を漂っていると考えられているそうです。教授たちは常に幼生たちはどこへいくのか、という疑問を考え続けていたと言います。
しかし今までは調査をするのは容易ではありませんでした。そこで研究者達は国際チームを作り問題解決にあたります。彼らが目をつけたのは母親でした。彼らはパプアニューギニアの Kimbe Bay(キンベ湾)からメスの魚を集め barium isotope を注入しました。アイソトープは骨などに蓄積され子供に伝わります。
数週間後チームはサンゴ礁に戻り小さい魚を採集し彼らに「しるし」があるか調査したところ、60パーセントが元の場所に戻っていることが確認されたのです。これは予期せぬ結果だと教授は語っています。
この2種類の熱帯魚がどのように生まれ故郷に戻るのかはまだはっきりと分かっておらず、今後も研究を続けていきたいと研究者は語ります。おそらくはホームアイランドを感じる何らかの感覚があって自分達の位置を確認することができ遠くまで漂うことはないか、遠くまで流されても帰巣のメカニズムが働きもとの場所に泳いで戻ってくることができるのではないかと
Jones 教授は言います。
教授はこの発見は他の熱帯魚にも当てはまり、もしそうであれば魚の持ち出し禁止区域をつくることは、乱獲された魚を保護するために有効な方法ではないかと考えています。というのもそこには数を維持するのに十分な幼魚が戻ってくるはずだからと彼は言います。
◆◇◆
2003年に日本でも公開された映画「ファインディング・ニモ」のせいでカクレクマノミやナンヨウハギが乱獲されていると一時期話題になっていましたが今海の中はどうなっているのでしょうか。
一方岡山理科大専門学校でクマノミの大量養殖に成功し販売ルートに乗りつつあるというニュースもありますが・・・。
癒されるならニモグッズで

キュービーはカワイイ人気のキャラクターを四角いのミュージックロボット。顔を“パコパコ”さ...

3Pボーイズブリーフニモ4・6才
Posted by うおみ at 18:00│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。