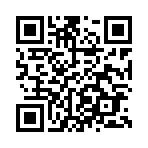2007年05月25日
魚はどうやって陸に上がったかの謎をとけ・・・という話
こんなニュース見つけちゃいました。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
23 May 2007 BBC News
太古の昔どうやって水にすむ魚が陸に上がったのかという謎に対して遺伝学的研究がすすめられているそうです。
以前の研究では魚は突然変異によって足を得たと考えられてきました。しかしアメリカの研究チームは変化は非常にゆっくりであったことを示そうとしています。
この研究は、ヒレと足をつなぐ "missing link" をもつ化石が発見されたことによって始められました。それは Tiktaalik roseae と呼ばれる3億8千万年前に生きていたワニに似た生物の化石で2004年に発見されました。そのヒレは水中で暮らすためのものであると同時に陸上での活動にも使われていたことが明らかになっています。
University of Chicago(シカゴ大学)の主任研究者 Marcus Davis 教授はこうした化石は、陸上生物の手足や指などがどこからともなく現れてきたわけではないことを示していると語ります。彼らの研究では Hox
genes(ホックス遺伝子)という手足の発達に重要な役割を果たす遺伝子に注目しました。
教授たちは陸上の四肢動物の足の発生とゼブラフィッシュのヒレの発生にかかわる遺伝子の発現を研究します。四肢動物の場合、ホックス遺伝子によって手足などの付属器官が形成されていく過程は2段階に分かれ、発生の初期が第一段階、その後第二段階で指がどこに来るか、など特徴づけがなされていくそうです。しかしゼブラフィッシュの場合、第一段階はありますが、顕著な特徴を形成する第二段階はみられませんでした。
このことから教授はホックス遺伝子の発現の第二段階が手足の起源に関連するのでないかと仮定します。
Davis 教授は paddlefish(ヘラチョウザメ)を使って研究を続けました。この魚のヒレは原始的な魚のヒレとよく似た形体を持っているのです。教授によるとこの魚のヒレには明らかに第二段階の過程が見受けられ、このことはホックス遺伝子の発現の第二段階は実際は、はるか古代の進化のパターンだったことを物語っていると言います。
ある種の魚はヒレを変えていく遺伝的なツールキットを持っており、何らかの環境の変化によって深い水中から浅瀬に移動した魚たちには遺伝的に足を作る能力が現れたのではないかと教授は考えているのです。
Davis 教授はこの研究によってゼブラフィッシュの奇妙さが明らかになったことも興味深いと語ります。教授によるとこの魚は非常に独特な進化をとげ、ホックス遺伝子の発現の第二段階を失ってしまったかのようだと語っています。
◆◇◆
化石を調べてそんなに色々なことが分かるのだろうかとふと思うのですが、保存状態のいい化石からは現在の生物に見られるような器官の前の段階の痕跡が残っている場合があるのだとか。これからも様々な発見があるんでしょうね。
化石を探す旅にでも行こうか・・・
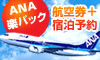
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
23 May 2007 BBC News
太古の昔どうやって水にすむ魚が陸に上がったのかという謎に対して遺伝学的研究がすすめられているそうです。
以前の研究では魚は突然変異によって足を得たと考えられてきました。しかしアメリカの研究チームは変化は非常にゆっくりであったことを示そうとしています。
この研究は、ヒレと足をつなぐ "missing link" をもつ化石が発見されたことによって始められました。それは Tiktaalik roseae と呼ばれる3億8千万年前に生きていたワニに似た生物の化石で2004年に発見されました。そのヒレは水中で暮らすためのものであると同時に陸上での活動にも使われていたことが明らかになっています。
University of Chicago(シカゴ大学)の主任研究者 Marcus Davis 教授はこうした化石は、陸上生物の手足や指などがどこからともなく現れてきたわけではないことを示していると語ります。彼らの研究では Hox
genes(ホックス遺伝子)という手足の発達に重要な役割を果たす遺伝子に注目しました。
教授たちは陸上の四肢動物の足の発生とゼブラフィッシュのヒレの発生にかかわる遺伝子の発現を研究します。四肢動物の場合、ホックス遺伝子によって手足などの付属器官が形成されていく過程は2段階に分かれ、発生の初期が第一段階、その後第二段階で指がどこに来るか、など特徴づけがなされていくそうです。しかしゼブラフィッシュの場合、第一段階はありますが、顕著な特徴を形成する第二段階はみられませんでした。
このことから教授はホックス遺伝子の発現の第二段階が手足の起源に関連するのでないかと仮定します。
Davis 教授は paddlefish(ヘラチョウザメ)を使って研究を続けました。この魚のヒレは原始的な魚のヒレとよく似た形体を持っているのです。教授によるとこの魚のヒレには明らかに第二段階の過程が見受けられ、このことはホックス遺伝子の発現の第二段階は実際は、はるか古代の進化のパターンだったことを物語っていると言います。
ある種の魚はヒレを変えていく遺伝的なツールキットを持っており、何らかの環境の変化によって深い水中から浅瀬に移動した魚たちには遺伝的に足を作る能力が現れたのではないかと教授は考えているのです。
Davis 教授はこの研究によってゼブラフィッシュの奇妙さが明らかになったことも興味深いと語ります。教授によるとこの魚は非常に独特な進化をとげ、ホックス遺伝子の発現の第二段階を失ってしまったかのようだと語っています。
◆◇◆
化石を調べてそんなに色々なことが分かるのだろうかとふと思うのですが、保存状態のいい化石からは現在の生物に見られるような器官の前の段階の痕跡が残っている場合があるのだとか。これからも様々な発見があるんでしょうね。
化石を探す旅にでも行こうか・・・
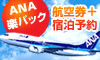
Posted by うおみ at 19:05│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。