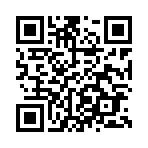2008年09月03日
サンゴと海草の微妙な関係とは?・・・という話
こんなニュース見つけちゃいました。お魚ニュースといいつつ本日はサンゴの話です。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Sydney September 2, 2008 SmasHits
ある種の海草が出す化学物質はサンゴの成長を阻害することが分かったそうです。
オーストラリアは ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies (CoECRS) の Laurence McCook 博士を中心とする研究グループはある海草や藻が作り出す有害化学物質はサンゴの幼生が白化によって荒れてしまったリーフに住み着くことを妨害する事を発見しました。そして一方この化学物質を使って新しい快適な住まいを見つける抜け目のないサンゴの幼生がいることも分かったそうです。
水中に放出される藻の化学物質はダメージを受けたサンゴの回復に大きな影響を与えるといいます。研究チームが3種類の海草で試したところ、Turtle Weed と呼ばれる海草はサンゴの幼生の定着を阻止する上で非常に大きな影響力があることが分かりました。サンゴの幼生は2種類目の海草の生み出す物質にも阻害され、3種類目にやっと定着することができたといいます。
これらの化学物質のメカニズムは世界中のサンゴ礁が長期的に生き残り、白化によるダメージから再生する能力に大きく関係している可能性があると研究チームのメンバーは語ります。
McCook 博士によるとサンゴ礁がダメージを受けた後に藻がサンゴに勝って荒れたエリアに定着している場所が多いといいます。そのうち多くはどんな種類の藻が新システムを支配するかそしてその周辺には海草を食べる魚やウミガメなどが多く存在するかどうかにかかっており、そこにはサンゴが再生するチャンスもあるのです。
最大の脅威となっているのは多量の堆積物が流入し藻がはびこった状態だといいます。そうなるとリーフは窒息し、サンゴは地盤を固めることができなくなってしまうのです。これは沿岸のリーフにとって深刻な問題となっていると McCook 博士は語っています。
どの種類の海草がどの程度影響を与えるのかについてまだはっきりと分かっているわけではないようです。化学物質の与える影響についてはこれまであまり研究されておらず、今後リーフのケアを続けサンゴに生存のチャンスを与えるためにもこれらの影響について理解することが必要だと博士は語っています。
◆◇◆
サンゴは一度白化しても時期が短ければ復活できるそうですね。ただ白化状態が長期にわたるとエサ不足により死滅してしまうそうです。研究が進んで「サンゴの定着を促す物質を作り出す海草」みたいなのが分かってくればサンゴ礁を復活させる試みも幅が広がるのではないでしょうか。
サンゴとは関係ないですがこんなニュースを見つけました。熊野灘の鯨類追い込み網漁が解禁となり和歌山県太地町沖で約10頭を捕獲したそうです。捕獲したのは体長3~5メートルのマゴンドウで2日朝競りにかけられるとのこと。捕獲可能なのは7種類の鯨類で頭数制限もあり今季は昨季より75頭少ない2393頭だそうです。
大昔給食でクジラを食べたことを思い出します。


サンゴとサンゴ礁のはなし 南の海のふしぎな生態系



サンゴ礁の世界

ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Sydney September 2, 2008 SmasHits
ある種の海草が出す化学物質はサンゴの成長を阻害することが分かったそうです。
オーストラリアは ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies (CoECRS) の Laurence McCook 博士を中心とする研究グループはある海草や藻が作り出す有害化学物質はサンゴの幼生が白化によって荒れてしまったリーフに住み着くことを妨害する事を発見しました。そして一方この化学物質を使って新しい快適な住まいを見つける抜け目のないサンゴの幼生がいることも分かったそうです。
水中に放出される藻の化学物質はダメージを受けたサンゴの回復に大きな影響を与えるといいます。研究チームが3種類の海草で試したところ、Turtle Weed と呼ばれる海草はサンゴの幼生の定着を阻止する上で非常に大きな影響力があることが分かりました。サンゴの幼生は2種類目の海草の生み出す物質にも阻害され、3種類目にやっと定着することができたといいます。
これらの化学物質のメカニズムは世界中のサンゴ礁が長期的に生き残り、白化によるダメージから再生する能力に大きく関係している可能性があると研究チームのメンバーは語ります。
McCook 博士によるとサンゴ礁がダメージを受けた後に藻がサンゴに勝って荒れたエリアに定着している場所が多いといいます。そのうち多くはどんな種類の藻が新システムを支配するかそしてその周辺には海草を食べる魚やウミガメなどが多く存在するかどうかにかかっており、そこにはサンゴが再生するチャンスもあるのです。
最大の脅威となっているのは多量の堆積物が流入し藻がはびこった状態だといいます。そうなるとリーフは窒息し、サンゴは地盤を固めることができなくなってしまうのです。これは沿岸のリーフにとって深刻な問題となっていると McCook 博士は語っています。
どの種類の海草がどの程度影響を与えるのかについてまだはっきりと分かっているわけではないようです。化学物質の与える影響についてはこれまであまり研究されておらず、今後リーフのケアを続けサンゴに生存のチャンスを与えるためにもこれらの影響について理解することが必要だと博士は語っています。
◆◇◆
サンゴは一度白化しても時期が短ければ復活できるそうですね。ただ白化状態が長期にわたるとエサ不足により死滅してしまうそうです。研究が進んで「サンゴの定着を促す物質を作り出す海草」みたいなのが分かってくればサンゴ礁を復活させる試みも幅が広がるのではないでしょうか。
サンゴとは関係ないですがこんなニュースを見つけました。熊野灘の鯨類追い込み網漁が解禁となり和歌山県太地町沖で約10頭を捕獲したそうです。捕獲したのは体長3~5メートルのマゴンドウで2日朝競りにかけられるとのこと。捕獲可能なのは7種類の鯨類で頭数制限もあり今季は昨季より75頭少ない2393頭だそうです。
大昔給食でクジラを食べたことを思い出します。

サンゴとサンゴ礁のはなし 南の海のふしぎな生態系

サンゴ礁の世界
Posted by うおみ at 14:56│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。