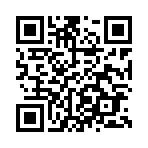2008年11月20日
役に立つ深海生物の話
こんなニュース見つけちゃいました。お魚ニュースといいつつ本日は緑色に光る生物の話です。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら(妖しく光る生物の写真が載ってます。)
Nov. 19, 2008 ScienceDaily
イソギンチャクやサンゴなど多くの海洋生物は様々な色に輝く蛍光タンパク質を作り出します。この物質はバイオメディカルの研究に画期的な変革をもたらしました。蛍光タンパク質を細胞に導入し、細胞や分子の活動を可視化できるようにするイメージングの研究が進んだのです。
数多くの有用な蛍光タンパク質は日の光があふれる熱帯のサンゴ礁で発見されていますが、深海に生息する生物もこの物質を作ることはあまり知られていません。
イギリスは Southampton(サウサンプトン) の National Oceano-
graphy Centre(英国海洋センター) の Jorg Wiedenmann 氏率いる国際研究チームは蛍光物質を持つ生物を探し出す装置を装着した潜水艦 US Johnson-Sea-Link II を使いメキシコ湾を調査しました。
彼らは明るいグリーンの蛍光を発するイソギンチャクに似た生物を発見します。この生物は新種の可能性があり新しいグリーンの蛍光タンパク質を確認できたそうです。
cerFP505 と名づけられた新しいタンパク質は500メートルから600メートルの間の真っ暗で水温の低い深海に住む生物から抽出されたにもかかわらず、タンパク質マーカーとして体温37度の哺乳類でも有効に働くことが分かったのです。
研究の結果この物質にブルーのライトや近紫外線をあてると光る状態となり、他の蛍光タンパク質よりも長い間その状態を保つことができ、オンとオフの切り替えが早いことが分かりました。こうした特性により超解像顕微鏡法の新しいタイプのマーカータンパク質として期待されているそうです。
この新蛍光タンパク質が深海の生物から発見されたことによって深海はイメージング技術にとって新しく望ましい特性を持つタンパク質の宝庫である可能性を示していると科学者は語っているとのこと。
◆◇◆
蛍光タンパク質というと下村脩博士が先日ノーベル化学賞を受賞されたニュースが記憶に新しいところですね。博士がこの物質を取り出したことで一躍脚光を浴びることになったのがオワンクラゲでした。山形県の鶴岡市立加茂水族館では11月1日よりこのクラゲの発光実験に取り組みその様子を展示しているそうです。
イソギンチャクとは関係ありませんがこんなニュースを見つけました。和歌山県白浜町の日置川河口で南方系の魚が釣り上げられたそうです。その魚は体長14.4センチの「ハナフエフキ」という種類で、紀南でよく見られる「ハマフエフキ」とは違い、亜熱帯、熱帯域に生息する種類とのこと。釣り上げた京都大学瀬戸臨海実験所の元教員によると、最近南方系の魚がよく見られるようになったが温暖化の影響だろうと話しているそうです。


バイオイメージングがわかる 細胞内分子を観察する多様な技術とその原理



生物と無生物のあいだ

ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら(妖しく光る生物の写真が載ってます。)
Nov. 19, 2008 ScienceDaily
イソギンチャクやサンゴなど多くの海洋生物は様々な色に輝く蛍光タンパク質を作り出します。この物質はバイオメディカルの研究に画期的な変革をもたらしました。蛍光タンパク質を細胞に導入し、細胞や分子の活動を可視化できるようにするイメージングの研究が進んだのです。
数多くの有用な蛍光タンパク質は日の光があふれる熱帯のサンゴ礁で発見されていますが、深海に生息する生物もこの物質を作ることはあまり知られていません。
イギリスは Southampton(サウサンプトン) の National Oceano-
graphy Centre(英国海洋センター) の Jorg Wiedenmann 氏率いる国際研究チームは蛍光物質を持つ生物を探し出す装置を装着した潜水艦 US Johnson-Sea-Link II を使いメキシコ湾を調査しました。
彼らは明るいグリーンの蛍光を発するイソギンチャクに似た生物を発見します。この生物は新種の可能性があり新しいグリーンの蛍光タンパク質を確認できたそうです。
cerFP505 と名づけられた新しいタンパク質は500メートルから600メートルの間の真っ暗で水温の低い深海に住む生物から抽出されたにもかかわらず、タンパク質マーカーとして体温37度の哺乳類でも有効に働くことが分かったのです。
研究の結果この物質にブルーのライトや近紫外線をあてると光る状態となり、他の蛍光タンパク質よりも長い間その状態を保つことができ、オンとオフの切り替えが早いことが分かりました。こうした特性により超解像顕微鏡法の新しいタイプのマーカータンパク質として期待されているそうです。
この新蛍光タンパク質が深海の生物から発見されたことによって深海はイメージング技術にとって新しく望ましい特性を持つタンパク質の宝庫である可能性を示していると科学者は語っているとのこと。
◆◇◆
蛍光タンパク質というと下村脩博士が先日ノーベル化学賞を受賞されたニュースが記憶に新しいところですね。博士がこの物質を取り出したことで一躍脚光を浴びることになったのがオワンクラゲでした。山形県の鶴岡市立加茂水族館では11月1日よりこのクラゲの発光実験に取り組みその様子を展示しているそうです。
イソギンチャクとは関係ありませんがこんなニュースを見つけました。和歌山県白浜町の日置川河口で南方系の魚が釣り上げられたそうです。その魚は体長14.4センチの「ハナフエフキ」という種類で、紀南でよく見られる「ハマフエフキ」とは違い、亜熱帯、熱帯域に生息する種類とのこと。釣り上げた京都大学瀬戸臨海実験所の元教員によると、最近南方系の魚がよく見られるようになったが温暖化の影響だろうと話しているそうです。

バイオイメージングがわかる 細胞内分子を観察する多様な技術とその原理

生物と無生物のあいだ
Posted by うおみ at 16:43│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。