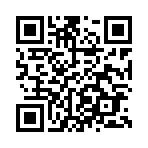2008年12月31日
サンゴが復活した!・・・という話
こんなニュース見つけちゃいました。お魚ニュースといいつつ本日の主人公はサンゴです。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Dec. 27, 2008 ScienceDaily
ニューヨークは Wildlife Conservation Society (WCS、野性動物保護協会) の科学者チームによると、2004年12月26日津波で大きな被害を被ったインドネシア地域のサンゴ礁が復活してきているそうです。
WCS 初め政府機関などからなる合同チームは津波以後インドネシアの Aceh(アチェ) を中心に800キロにわたる海岸線沿いの60ヶ所のサンゴ礁の調査を続けてきました。
津波の被害から4年目でここまで素早い回復を見せるとはすばらしいことだ、と WCS インドネシア・マリン・プログラムのコーディネーター Stuart Campbell 博士は語っています。「私達が観察したところ、津波がダメージをもたらした海域の若いサンゴはすごい速さの成長を見せており、同時にかつて破壊的な漁で被害を受けた海域のサンゴも新しい世代が育ってきています。この発見によってサンゴの復活過程への理解が進み、温暖化に直面したサンゴ礁を管理保護していく助けとなるでしょう。」と彼は語ります。
津波の後すぐに行われた調査ではサンゴ礁の部分的なダメージが発見されましたが、2005年の調査では死んだサンゴの多くがダイナマイトやシアン化物を使った漁のために大分前に死んだものであることが分かったのです。また広範囲にわたるサンゴが死んだ原因が crown of thorns starfish(オニヒトデ) にあることも分かりました。
その後いくつかの村では破壊的な漁をやめダメージを受けた海域にサンゴの移植を始めます。小さなところでは個人での活動が始められ、またより大きななスケールでは WCS チーム主導で地域ごとのサンゴ礁保護区をつくり1600年代に確立された慣習的な海洋法とオランダ法に基づいて管理し、サンゴの保護に努めることが決められたのです。
WCS では健康的なサンゴ礁は、アチェの共同体にとって商業的に大事な魚を提供し、観光によってドルをもたらす経済的な原動力となると考えています。この復興はサンゴの管理法の改善と地元の人々の協力の賜物であり、サンゴ礁が地元の人々を繁栄させる宝に満ちた以前の状態に戻ることができるという大きな希望を人々に与えるものだ、と Campbell 博士は語っています。
◆◇◆
この海域は "Coral Triangle"(サンゴ礁三角地帯) と呼ばれる世界中のサンゴの75パーセントが生息する海に隣接している貴重な場所とのこと。復活しつつあるというのは嬉しいニュースですね。
インドネシアのサンゴの養殖現場はこんな感じのようです。(YouTube)
サンゴとは関係ありませんがこんなニュースを見つけました。岡山市の池田動物園で30日「干支の引継ぎ式」が行われたそうです。式は同園飼育係が育てているハツカネズミの「ミルク」から牛の仲間であるキリンの「桃花」にバトンタッチされる「干支の委嘱状」を同園副園長が読み上げる形で進行。式は無事終了し「桃花」はお飾りをつけたカシの葉をプレゼントされたとのこと。
あっという間に2008年も終わりですね。今年もへたっぴな訳のニュースにお付き合い下さりありがとうございました。
陸上でも水中でも暗いニュースが多いなか少しでも楽しく、ほっとできるものを、と探してきたつもりですが如何だったでしょうか。
来年は明るい話をたくさんお届けできればと思います。
それではよいお年を。


サンゴ・レンジャー 南の島をまもる愛の物語



サンゴ礁の世界

ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Dec. 27, 2008 ScienceDaily
ニューヨークは Wildlife Conservation Society (WCS、野性動物保護協会) の科学者チームによると、2004年12月26日津波で大きな被害を被ったインドネシア地域のサンゴ礁が復活してきているそうです。
WCS 初め政府機関などからなる合同チームは津波以後インドネシアの Aceh(アチェ) を中心に800キロにわたる海岸線沿いの60ヶ所のサンゴ礁の調査を続けてきました。
津波の被害から4年目でここまで素早い回復を見せるとはすばらしいことだ、と WCS インドネシア・マリン・プログラムのコーディネーター Stuart Campbell 博士は語っています。「私達が観察したところ、津波がダメージをもたらした海域の若いサンゴはすごい速さの成長を見せており、同時にかつて破壊的な漁で被害を受けた海域のサンゴも新しい世代が育ってきています。この発見によってサンゴの復活過程への理解が進み、温暖化に直面したサンゴ礁を管理保護していく助けとなるでしょう。」と彼は語ります。
津波の後すぐに行われた調査ではサンゴ礁の部分的なダメージが発見されましたが、2005年の調査では死んだサンゴの多くがダイナマイトやシアン化物を使った漁のために大分前に死んだものであることが分かったのです。また広範囲にわたるサンゴが死んだ原因が crown of thorns starfish(オニヒトデ) にあることも分かりました。
その後いくつかの村では破壊的な漁をやめダメージを受けた海域にサンゴの移植を始めます。小さなところでは個人での活動が始められ、またより大きななスケールでは WCS チーム主導で地域ごとのサンゴ礁保護区をつくり1600年代に確立された慣習的な海洋法とオランダ法に基づいて管理し、サンゴの保護に努めることが決められたのです。
WCS では健康的なサンゴ礁は、アチェの共同体にとって商業的に大事な魚を提供し、観光によってドルをもたらす経済的な原動力となると考えています。この復興はサンゴの管理法の改善と地元の人々の協力の賜物であり、サンゴ礁が地元の人々を繁栄させる宝に満ちた以前の状態に戻ることができるという大きな希望を人々に与えるものだ、と Campbell 博士は語っています。
◆◇◆
この海域は "Coral Triangle"(サンゴ礁三角地帯) と呼ばれる世界中のサンゴの75パーセントが生息する海に隣接している貴重な場所とのこと。復活しつつあるというのは嬉しいニュースですね。
インドネシアのサンゴの養殖現場はこんな感じのようです。(YouTube)
サンゴとは関係ありませんがこんなニュースを見つけました。岡山市の池田動物園で30日「干支の引継ぎ式」が行われたそうです。式は同園飼育係が育てているハツカネズミの「ミルク」から牛の仲間であるキリンの「桃花」にバトンタッチされる「干支の委嘱状」を同園副園長が読み上げる形で進行。式は無事終了し「桃花」はお飾りをつけたカシの葉をプレゼントされたとのこと。
あっという間に2008年も終わりですね。今年もへたっぴな訳のニュースにお付き合い下さりありがとうございました。
陸上でも水中でも暗いニュースが多いなか少しでも楽しく、ほっとできるものを、と探してきたつもりですが如何だったでしょうか。
来年は明るい話をたくさんお届けできればと思います。
それではよいお年を。

サンゴ・レンジャー 南の島をまもる愛の物語

サンゴ礁の世界
Posted by うおみ at 11:33│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。