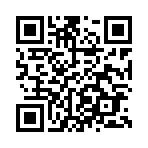2009年01月26日
そのエサに注意!・・・という話
こんなニュース見つけちゃいました。お魚ニュースといいつつ本日はラッコの話です。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Jan. 24, 2009 Science Daily
カリフォルニア中央部の沿岸に生息する sea otter(ラッコ) は食べるエサの種類とエサを捕る場所によって危険な寄生虫に感染するリスクが高くなることが分かったそうです。
小さなウミカタツムリの類を食べるラッコは他のエサを食べるラッコに比べると toxoplasma gondii(トキソプラズマ) といわれる病原性原虫に感染する率が高いことが分かりました。またカリフォルニアの San Simeon (サンシメオン)から Cambria(カンブリア) にかけての沿岸に生息するラッコはこの海域以外に住むものと比べるとさらに危険度が上がることも分かりました。
同様に Monterey Bay(モントレー湾) の南端に生息し二枚貝などを食べるラッコは別の病原性原虫である Sarcocystis neurona に感染するリスクが高いといいます。しかしアワビを大量に食べるラッコはどちらの原虫にも感染する率が低くなるそうです。
カリフォルニア中央部ではラッコの個体数の回復はあまり進んでいないといいます。というのもラッコの生息密度が高すぎるためです。食べ物が限られているためラッコたちはエサを確保する技を身に付けそれは母親から子供へと伝えられていきます。
その結果同じエリアに生息していてもそれぞれに違うエサを食べるようになり2種類の原虫への感染率が高くなってくるというのです。
University of California-Davis(カリフォルニア大学デービス校) の疫学学者である Christine Johnson 氏は、今回の発見によってラッコが選択したエサが彼らの健康に影響を与えることが分かったとし、少ない資源と高い率で発症する感染症があいまってラッコの生息数の回復を阻んでいる可能性があると語ります。
科学者にとってのチャレンジは寄生虫がどのようにラッコに寄生するのかを正確に見極めることだといいます。自然界の中で寄生虫を探すことはほとんど不可能に近く、感染ルートを確定することは至難の業なのです。
U.S. Geological Survey (USGS、アメリカ地質調査所) のラッコ専門家 Tim Tinker 氏は、ラッコの行動パターンと発症の関係を研究することで、医者がある人の習慣から病気のリスクを調べるのと同じように発病のメカニズムについて多くのことを推測していくことができるだろうと語っています。
◆◇◆
トキソプラズマはネコ科の動物、S. neurona はオポッサムを最終宿主とするそうです。これらの原虫は陸上が起源と考えられ海に排出されれば死んでしまい無脊椎動物のエサになるとのこと。無脊椎動物自身は影響はないそうですが回りまわって感染したエサを食べるとラッコは脳炎で死んでしまうそうです。
ラッコとは関係ありませんがこんなニュースを見つけました。茨城県行方市の商工会は霞ヶ浦に生息するアメリカナマズを使ったご当地バーガー「なめパックン」を作ったそうです。この外来ナマズはワカサギなどの在来種を食い荒らし問題となっている魚で、これまでにもこの魚を使った生ハム「湖(かわ)ふぐ」という商品が開発されているそうです。このバーガーは26日から市内の精肉店「ミート&フーズ旭屋」や観光物産館で販売される予定とのこと。


テーマで読み解く海の百科事典 ビジュアル版



日本全国海の友達に会いに行こう! かいじゅう

ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Jan. 24, 2009 Science Daily
カリフォルニア中央部の沿岸に生息する sea otter(ラッコ) は食べるエサの種類とエサを捕る場所によって危険な寄生虫に感染するリスクが高くなることが分かったそうです。
小さなウミカタツムリの類を食べるラッコは他のエサを食べるラッコに比べると toxoplasma gondii(トキソプラズマ) といわれる病原性原虫に感染する率が高いことが分かりました。またカリフォルニアの San Simeon (サンシメオン)から Cambria(カンブリア) にかけての沿岸に生息するラッコはこの海域以外に住むものと比べるとさらに危険度が上がることも分かりました。
同様に Monterey Bay(モントレー湾) の南端に生息し二枚貝などを食べるラッコは別の病原性原虫である Sarcocystis neurona に感染するリスクが高いといいます。しかしアワビを大量に食べるラッコはどちらの原虫にも感染する率が低くなるそうです。
カリフォルニア中央部ではラッコの個体数の回復はあまり進んでいないといいます。というのもラッコの生息密度が高すぎるためです。食べ物が限られているためラッコたちはエサを確保する技を身に付けそれは母親から子供へと伝えられていきます。
その結果同じエリアに生息していてもそれぞれに違うエサを食べるようになり2種類の原虫への感染率が高くなってくるというのです。
University of California-Davis(カリフォルニア大学デービス校) の疫学学者である Christine Johnson 氏は、今回の発見によってラッコが選択したエサが彼らの健康に影響を与えることが分かったとし、少ない資源と高い率で発症する感染症があいまってラッコの生息数の回復を阻んでいる可能性があると語ります。
科学者にとってのチャレンジは寄生虫がどのようにラッコに寄生するのかを正確に見極めることだといいます。自然界の中で寄生虫を探すことはほとんど不可能に近く、感染ルートを確定することは至難の業なのです。
U.S. Geological Survey (USGS、アメリカ地質調査所) のラッコ専門家 Tim Tinker 氏は、ラッコの行動パターンと発症の関係を研究することで、医者がある人の習慣から病気のリスクを調べるのと同じように発病のメカニズムについて多くのことを推測していくことができるだろうと語っています。
◆◇◆
トキソプラズマはネコ科の動物、S. neurona はオポッサムを最終宿主とするそうです。これらの原虫は陸上が起源と考えられ海に排出されれば死んでしまい無脊椎動物のエサになるとのこと。無脊椎動物自身は影響はないそうですが回りまわって感染したエサを食べるとラッコは脳炎で死んでしまうそうです。
ラッコとは関係ありませんがこんなニュースを見つけました。茨城県行方市の商工会は霞ヶ浦に生息するアメリカナマズを使ったご当地バーガー「なめパックン」を作ったそうです。この外来ナマズはワカサギなどの在来種を食い荒らし問題となっている魚で、これまでにもこの魚を使った生ハム「湖(かわ)ふぐ」という商品が開発されているそうです。このバーガーは26日から市内の精肉店「ミート&フーズ旭屋」や観光物産館で販売される予定とのこと。

テーマで読み解く海の百科事典 ビジュアル版

日本全国海の友達に会いに行こう! かいじゅう
Posted by うおみ at 14:48│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。