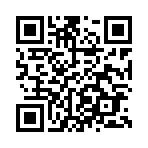2009年05月26日
生き残りをかけたサンゴの作戦とは・・・という話
こんなニュース見つけちゃいました。お魚ニュースといいつつ本日はサンゴの話です。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
26 May 2009 G-Online
地球温暖化による海水温の上昇に伴い、今後50年で世界のサンゴ礁の半分以上は消滅すると考えられていますが、近年温暖な環境に適応しつつあるサンゴがあることが発見され、研究が進められているようです。
Woods Institute for the Environment at Stanford University(スタンフォード大学ウッズ環境研究所) の生物学者 Stephen Palumbi 氏と研究チームのメンバーは太平洋のサンゴ礁の回復力について2006年から調査を始めました。
サンゴは褐虫藻と呼ばれる微細な単細胞の藻類と共生しています。サンゴは褐虫藻に住む場所を提供し、褐虫藻はサンゴに食べ物を作り出すいわゆる「共生」の関係を築いているのです。ところが海水温が上昇し褐虫藻がストレスを感じると食料を作り出すことをやめてしまいサンゴは褐虫藻を追い出します。サンゴは褐虫藻と共に色素を失い白く見えるようになります。これがサンゴの白化です。
近年サンゴの中には暑さに対処できる褐虫藻と共生することで白化をまぬがれたり、暑さにストレスを感じる褐虫藻からよりタフな褐虫藻にパートナーを変えるサンゴがあることが分かってきました。
Palumbi 氏らチームはこうした暑さに強いサンゴ礁が世界中にどれくらいあるのかを知り、強いタイプの褐虫藻が高い水温に適応する生物学的プロセスをより詳しく学ぶために調査を開始しました。
彼らは American Samoa(アメリカン・サモア) の island of Ofu(オフ島) で調査を開始します。ここのサンゴ礁は水温が次第に上がっているときも健康な状態を保っており、様々な水温のラグーンが存在し、そこに生息するサンゴを観察することができるのです。
比較的水温の低いラグーンでは暑さに強い褐虫藻を共生させているサンゴの割合はわずかですが、水温の高い場所ではその割合は増加することが分かりました。つまり熱さに敏感な褐虫藻からより強いタイプにパートナーを変えるサンゴがあることが示されたわけです。
通常水温が1度上がった状態が続くとほとんどのサンゴは白化するといいます。しかしこの暑さに強い褐虫藻は1.5度の変化まで耐えることができる可能性があるそうです。
彼らの最終的なゴールはサンゴが暑さによって感じるストレスや熱さに対する耐性を示す指標を見つけることだといいます。それが見つかればサンゴ礁の管理人はサンゴの小さなサンプルからいろいろなサインを読み取ることが出来ると彼らは語っています。
◆◇◆
水温が30度以上になるとサンゴの白化は進むそうです。またこれまでは台風によって海がかき回されることで海水温が低くなっていたそうですが、最近の台風は勢力が大きくサンゴ自信を傷つけてしまうことが増えているんだとか。
サンゴとは関係ありませんがこんなニュースを見つけました。国立科学博物館は26日から皇居の動植物について第2次調査を行うと発表したそうです。12年度まで実施し報告書をまとめるとのこと。前回の調査では動物3638種、植物1366種が生息していることが確認されたそうで、今回はタヌキなど特定の動物の生態を詳しく解析する計画もあるそうです。
絶滅危惧種も見つかっているようですが、新種などさらに見つかったらすごいですね。


南の島の自然誌 沖縄と小笠原の海洋生物研究のフィールドから



サンゴとサンゴ礁のはなし 南の海のふしぎな生態系

ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
26 May 2009 G-Online
地球温暖化による海水温の上昇に伴い、今後50年で世界のサンゴ礁の半分以上は消滅すると考えられていますが、近年温暖な環境に適応しつつあるサンゴがあることが発見され、研究が進められているようです。
Woods Institute for the Environment at Stanford University(スタンフォード大学ウッズ環境研究所) の生物学者 Stephen Palumbi 氏と研究チームのメンバーは太平洋のサンゴ礁の回復力について2006年から調査を始めました。
サンゴは褐虫藻と呼ばれる微細な単細胞の藻類と共生しています。サンゴは褐虫藻に住む場所を提供し、褐虫藻はサンゴに食べ物を作り出すいわゆる「共生」の関係を築いているのです。ところが海水温が上昇し褐虫藻がストレスを感じると食料を作り出すことをやめてしまいサンゴは褐虫藻を追い出します。サンゴは褐虫藻と共に色素を失い白く見えるようになります。これがサンゴの白化です。
近年サンゴの中には暑さに対処できる褐虫藻と共生することで白化をまぬがれたり、暑さにストレスを感じる褐虫藻からよりタフな褐虫藻にパートナーを変えるサンゴがあることが分かってきました。
Palumbi 氏らチームはこうした暑さに強いサンゴ礁が世界中にどれくらいあるのかを知り、強いタイプの褐虫藻が高い水温に適応する生物学的プロセスをより詳しく学ぶために調査を開始しました。
彼らは American Samoa(アメリカン・サモア) の island of Ofu(オフ島) で調査を開始します。ここのサンゴ礁は水温が次第に上がっているときも健康な状態を保っており、様々な水温のラグーンが存在し、そこに生息するサンゴを観察することができるのです。
比較的水温の低いラグーンでは暑さに強い褐虫藻を共生させているサンゴの割合はわずかですが、水温の高い場所ではその割合は増加することが分かりました。つまり熱さに敏感な褐虫藻からより強いタイプにパートナーを変えるサンゴがあることが示されたわけです。
通常水温が1度上がった状態が続くとほとんどのサンゴは白化するといいます。しかしこの暑さに強い褐虫藻は1.5度の変化まで耐えることができる可能性があるそうです。
彼らの最終的なゴールはサンゴが暑さによって感じるストレスや熱さに対する耐性を示す指標を見つけることだといいます。それが見つかればサンゴ礁の管理人はサンゴの小さなサンプルからいろいろなサインを読み取ることが出来ると彼らは語っています。
◆◇◆
水温が30度以上になるとサンゴの白化は進むそうです。またこれまでは台風によって海がかき回されることで海水温が低くなっていたそうですが、最近の台風は勢力が大きくサンゴ自信を傷つけてしまうことが増えているんだとか。
サンゴとは関係ありませんがこんなニュースを見つけました。国立科学博物館は26日から皇居の動植物について第2次調査を行うと発表したそうです。12年度まで実施し報告書をまとめるとのこと。前回の調査では動物3638種、植物1366種が生息していることが確認されたそうで、今回はタヌキなど特定の動物の生態を詳しく解析する計画もあるそうです。
絶滅危惧種も見つかっているようですが、新種などさらに見つかったらすごいですね。

南の島の自然誌 沖縄と小笠原の海洋生物研究のフィールドから

サンゴとサンゴ礁のはなし 南の海のふしぎな生態系
Posted by うおみ at 16:42│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。