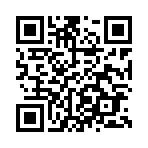2007年12月23日
姿を消したウナギの謎を解け!・・・という話
こんなニュース見つけちゃいました。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Dec. 21, 2007 Science Daily
カナダは Queen's University(クイーンズ大学) の科学者達は、
American eels(アメリカウナギ) が Lake Ontario(オンタリオ湖) の化学物質に汚染されているかどうかについて調査を開始するとのこと。
生物学者 Peter Hodson 教授と毒物学者、化学者からなる研究チームは Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC、カナダ自然科学工学研究機構) から補助金の交付を受けオンタリオ湖から消え去りつつあるアメリカウナギに関する謎を解くよう依頼されたそうです。
アメリカウナギはウナギ属に属する細長い魚で、世界中にその美味しさが知られています。カナダの Species at Risk Act(絶滅危惧種法) で「注意種」に指定され現在までオンタリオやケベックの水産業者に保護されてきました。しかしここ数年ウナギの数が激減し、オンタリオの業者は廃業に追いこまれ、ケベックでもその数は減少しているのです。
魚がいなくなる主な理由として疑わしいのは汚染された湖や川で成長した親ウナギに毒性の化学物質が蓄積していくことだと Hodson 教授は語ります。そして自分達の仕事は、オンタリオ湖に到着する前に死んでしまうほどの化学物質がメスのウナギからその稚魚に受け渡されるのかどうかについて確定することだろう、と言います。
彼らは清浄な場所、汚染された場所を含め様々な生息地のウナギの組織を調べ、化学物質の濃度や毒性を比較して過去の汚染状況を明確にする予定とのこと。
アメリカウナギは Bermuda(バミューダ島)の隣の Sargasso Sea(サルガッソー海)で孵化し何年もかけて淡水の川に上ってきます。そこで1メートルもの大きさに成長すると、生まれた場所に戻っていき産卵して一生を終えるのです。1980年代半ばごろからサルガッソー海からオンタリオ湖まで上ってくるウナギの稚魚の数が劇的に減ってきておりそれにともなって大人のウナギの数も減っているのです。
漁獲されたウナギの大半は各国に輸出されています。特に西ヨーロッパやアジアが多く、燻製、煮こごり、マリネ、すし種として食べられているとのこと。供給が減るにつれ値段も上がってきているそうです。
◆◇◆
ウナギはよく食べられているのにその生態は謎に満ちているんですね。20世紀になりやっと大西洋のウナギの産卵場所がサルガッソー海であることが分かったのだとか。しかしなぜアメリカやヨーロッパの川目指して長旅をするのかは分かっていないそうです。
ちなみにこちらのページにうなぎについて色々と載っています。


海のミネラル学 生物との関わりと利用



うなぎでワインが飲めますか? そば、てんぷら、チョコレートまでのワイン相性術

ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Dec. 21, 2007 Science Daily
カナダは Queen's University(クイーンズ大学) の科学者達は、
American eels(アメリカウナギ) が Lake Ontario(オンタリオ湖) の化学物質に汚染されているかどうかについて調査を開始するとのこと。
生物学者 Peter Hodson 教授と毒物学者、化学者からなる研究チームは Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC、カナダ自然科学工学研究機構) から補助金の交付を受けオンタリオ湖から消え去りつつあるアメリカウナギに関する謎を解くよう依頼されたそうです。
アメリカウナギはウナギ属に属する細長い魚で、世界中にその美味しさが知られています。カナダの Species at Risk Act(絶滅危惧種法) で「注意種」に指定され現在までオンタリオやケベックの水産業者に保護されてきました。しかしここ数年ウナギの数が激減し、オンタリオの業者は廃業に追いこまれ、ケベックでもその数は減少しているのです。
魚がいなくなる主な理由として疑わしいのは汚染された湖や川で成長した親ウナギに毒性の化学物質が蓄積していくことだと Hodson 教授は語ります。そして自分達の仕事は、オンタリオ湖に到着する前に死んでしまうほどの化学物質がメスのウナギからその稚魚に受け渡されるのかどうかについて確定することだろう、と言います。
彼らは清浄な場所、汚染された場所を含め様々な生息地のウナギの組織を調べ、化学物質の濃度や毒性を比較して過去の汚染状況を明確にする予定とのこと。
アメリカウナギは Bermuda(バミューダ島)の隣の Sargasso Sea(サルガッソー海)で孵化し何年もかけて淡水の川に上ってきます。そこで1メートルもの大きさに成長すると、生まれた場所に戻っていき産卵して一生を終えるのです。1980年代半ばごろからサルガッソー海からオンタリオ湖まで上ってくるウナギの稚魚の数が劇的に減ってきておりそれにともなって大人のウナギの数も減っているのです。
漁獲されたウナギの大半は各国に輸出されています。特に西ヨーロッパやアジアが多く、燻製、煮こごり、マリネ、すし種として食べられているとのこと。供給が減るにつれ値段も上がってきているそうです。
◆◇◆
ウナギはよく食べられているのにその生態は謎に満ちているんですね。20世紀になりやっと大西洋のウナギの産卵場所がサルガッソー海であることが分かったのだとか。しかしなぜアメリカやヨーロッパの川目指して長旅をするのかは分かっていないそうです。
ちなみにこちらのページにうなぎについて色々と載っています。

海のミネラル学 生物との関わりと利用

うなぎでワインが飲めますか? そば、てんぷら、チョコレートまでのワイン相性術
Posted by うおみ at 15:41│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。