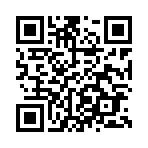2007年05月10日
よみがえった海の生き物達の話
こんなニュース見つけちゃいました。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Wednesday May 09, 2007 nzherald.co.nz
ニュージーランドの Goat Island (ゴートアイランド)は Cape Rodney - Okakari Point 海洋保護区域にあり、今でこそたくさんの魚が泳ぎ観光客も多数やってきますが、30年前はこうではなかったそうです。
6メートルほどの水深の岩だなはウニのために荒れ果てていました。ウニは天敵の snapper (タイの類) や crayfish (ザリガニの類)がいないためケルプの森を食べつくしてしまったのです。これはノースランド地方ではよくあることと考えられていたのです。
1965年、University of Auckland(オークランド大学) の海洋研究所のスタッフは、人々が研究対象を捕獲したり傷つけたりしない場所で研究をしたいと研究所の近くのサンゴ礁と砂質干潟を保護したいと考えます。
当時は海洋保護など聞いたこともなく規制法もありませんでした。Val
Chapman と John Morton の両教授は Dr Bill Ballantine の助けも得てお役所仕事と反対の声と戦い、ついに1977年5月ニュージーランド発の海洋保護区が正式にオープンしたのです。
海洋保護区による恩恵は明らかでした。今や夏のシーズンには3000人もの人々がビーチに押し寄せます。保護が始まった当初は、釣りや貝などの採取目的以外に人々がビーチにやってくることなど誰も考えなかったのです。
当初この保護区の設立は研究目的であったものの、次第にツーリズムや教育などにも影響がおよんできました。グラスボート、教育センター、ダイブショップ、レストラン、宿泊施設等が作られ人々が集まります。保護区域の面積はわずか5スクエアキロメートルですがインパクトは大きなものでした。
snapper や crayfish の数がかなり増えたせいでウニの数は減ってきています。それと同時にケルプの森も戻ってきてその周りに住む魚や無脊椎動物も増えています。保護区を設定しなければこれはありえなかったでしょう。
red moki (タカノハダイの類)や butterfish(バターフィッシュ) は以前は珍しい種類でしたが、今では周囲の海岸よりも数は多くなっているそうです。保護区ができるまではほとんど姿を消していたSilver drummer(イスズミの類) は戻ってくるのに時間がかかりました。10年前はサイズも小さく、気まぐれに現れたりするだけだったのですが、今では形も大きくなり悠々と泳ぎ回っています。ケルプを食べるParore(メジナの類)も浅瀬にたくさんいます。
この保護区はオープンして30年経ちますが、そこにすむ生物の数は変動を続けています。snapper や crayfish の数は科学者によって記録され、他の種類の生物についてはいつもこの区域に潜っているダイバーとシュノーケラーがチェックしているとのこと。
この保護区が制定されたことで人々は、海を保護することによって恩恵を得ることができると同時に、海洋生物を保護するのは一朝一夕ではできないということを学んだのではないか、とのことでした。
◆◇◆
この保護区では魚の数が増えたのみならず他の地域と比べてサイズも大きく、あまり人を恐れないのだそうです。禁漁区域なので釣り上げられることもなく食べ物も豊富で、魚にとってパラダイスであると同時にヒトにとっても竜宮城気分を味わえるすばらしい場所のようです。ぜひ一度ウオミをしたいものです。


熟年スクーバダイビング開眼 おさかな気分満喫!



ニュージーランド北島 自然の造形美とマオリ文化に浸る

ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
Wednesday May 09, 2007 nzherald.co.nz
ニュージーランドの Goat Island (ゴートアイランド)は Cape Rodney - Okakari Point 海洋保護区域にあり、今でこそたくさんの魚が泳ぎ観光客も多数やってきますが、30年前はこうではなかったそうです。
6メートルほどの水深の岩だなはウニのために荒れ果てていました。ウニは天敵の snapper (タイの類) や crayfish (ザリガニの類)がいないためケルプの森を食べつくしてしまったのです。これはノースランド地方ではよくあることと考えられていたのです。
1965年、University of Auckland(オークランド大学) の海洋研究所のスタッフは、人々が研究対象を捕獲したり傷つけたりしない場所で研究をしたいと研究所の近くのサンゴ礁と砂質干潟を保護したいと考えます。
当時は海洋保護など聞いたこともなく規制法もありませんでした。Val
Chapman と John Morton の両教授は Dr Bill Ballantine の助けも得てお役所仕事と反対の声と戦い、ついに1977年5月ニュージーランド発の海洋保護区が正式にオープンしたのです。
海洋保護区による恩恵は明らかでした。今や夏のシーズンには3000人もの人々がビーチに押し寄せます。保護が始まった当初は、釣りや貝などの採取目的以外に人々がビーチにやってくることなど誰も考えなかったのです。
当初この保護区の設立は研究目的であったものの、次第にツーリズムや教育などにも影響がおよんできました。グラスボート、教育センター、ダイブショップ、レストラン、宿泊施設等が作られ人々が集まります。保護区域の面積はわずか5スクエアキロメートルですがインパクトは大きなものでした。
snapper や crayfish の数がかなり増えたせいでウニの数は減ってきています。それと同時にケルプの森も戻ってきてその周りに住む魚や無脊椎動物も増えています。保護区を設定しなければこれはありえなかったでしょう。
red moki (タカノハダイの類)や butterfish(バターフィッシュ) は以前は珍しい種類でしたが、今では周囲の海岸よりも数は多くなっているそうです。保護区ができるまではほとんど姿を消していたSilver drummer(イスズミの類) は戻ってくるのに時間がかかりました。10年前はサイズも小さく、気まぐれに現れたりするだけだったのですが、今では形も大きくなり悠々と泳ぎ回っています。ケルプを食べるParore(メジナの類)も浅瀬にたくさんいます。
この保護区はオープンして30年経ちますが、そこにすむ生物の数は変動を続けています。snapper や crayfish の数は科学者によって記録され、他の種類の生物についてはいつもこの区域に潜っているダイバーとシュノーケラーがチェックしているとのこと。
この保護区が制定されたことで人々は、海を保護することによって恩恵を得ることができると同時に、海洋生物を保護するのは一朝一夕ではできないということを学んだのではないか、とのことでした。
◆◇◆
この保護区では魚の数が増えたのみならず他の地域と比べてサイズも大きく、あまり人を恐れないのだそうです。禁漁区域なので釣り上げられることもなく食べ物も豊富で、魚にとってパラダイスであると同時にヒトにとっても竜宮城気分を味わえるすばらしい場所のようです。ぜひ一度ウオミをしたいものです。

熟年スクーバダイビング開眼 おさかな気分満喫!

ニュージーランド北島 自然の造形美とマオリ文化に浸る
Posted by うおみ at 15:56│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。