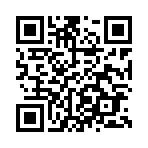2008年09月19日
目と鼻の先にいた!・・・という話
こんなニュース見つけちゃいました。お魚ニュースといいつつ本日は新種大量発見の話です。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら(一部写真が載ってます。)
September 19, 2008 TIMESONLINE
オーストラリアでも最も人が訪れるサンゴ礁で何百種もの新種の生物が発見されたそうです。
今回の調査は Census of Marine Life(海洋生物のセンサス) に参加した科学者によって行われました。数多くの生物達が研究ステーションのすぐ近くにいる科学者やダイバー、グレートバリアリーフのプロのガイドの隣を泳いでいたわけですが誰もこれまでその重要性を認識していなかったのです。
新種が確認されたのはノースウェスト沖の Ningaloo Reef(ニンガルーリーフ) とノースイースト沖の Lizard islands(リザード島)、Heron is-
lands(ヘロン島) 沖で、リーフとは反対側を調査している時でした。
今回の調査は isopods(フナムシの類) やソフト・コーラル、ワームなどほとんど同定がされていない生物を中心に行われました。魚やハードコーラル、サメ、ウミウシといった生物についてはすでにまとめられているため省かれました。
「印象的だったのはこれほどの数の種類が目の前にいたことです。このあたりの場所は何年もの間人々がダイビングし研究ステーションも設置していたのです。」と Australian Institute of Marine Science(オーストラリア海洋科学研究所) の Julian Caley 氏は語っています。
彼は3回の調査で見つかったおよそ1000種類以上の生物のうち300から500は新種であると考えています。そしてまたさらにあと2年間の調査で更なる発見があるだろうと期待しているといいます。
これから詳細な分析は必要ですが、新種と考えられるのはソフト・コーラル150種、甲殻類130種、ワーム100種類ほどだといいます。新種のウニ、basket stars(テズルモズル)、海草でも新たな発見がありました。
今回発見された新種の中で特に研究チームの興味を惹いたものはフナムシの仲間だそうです。この生物は体長わずか数ミリしかなく、貴重な多様性のインジケーターであると考えられるからです。また彼らはこの生物の生きた魚の舌を食べるという不思議な生態を確認したいとも考えているようです。
同センサスのチーフ・サイエンティストである Ron O’Dor 氏は「リーフに住む驚くほどカラフルなサンゴや魚に長い間ダイバー達は目を奪われてきましたが、今回の調査でこの場所にはそれ以外にも実にたくさんの生物が暮らしていることに気づかされました。」と語っています。
海洋生物センサスは80カ国以上の国の科学者が参加するネットワークで今回の調査は4年にわたる研究プロジェクトの一環です。その目的は研究者が海洋環境の変化が及ぼす影響をより良く知ることができるように海洋生物について調査し幅広い基本的情報を提供することとのこと。
◆◇◆
海の生態系というのはそれほど幅広いということなのでしょうね。(海だけじゃないのかもしれませんが。)今回注目されているのはフナムシの仲間でタン・バイターとも言うべき寄生生物だそうで、生きた魚の舌を食べてしまい自分でその魚の口に取り付いて新たな舌になってしまうという摩訶不思議な生物とのこと。
新種とは関係ありませんが興味深いニュースを見つけました。なんでも弥生人はコイを飼って食料にしていた可能性があることが分かったそうです。滋賀県立琵琶湖博物館が愛知県の弥生時代中期の「朝日遺跡」を調査したところ、コイの幼魚と成魚の咽頭歯がみつかったとのこと。同博物館では幼魚を大量に捕獲するのは難しいため集落の環濠や水路などで養殖していたのではないかとみているそうです。古代中国ではコイの養殖方法を記した文献が見つかっているためこの技術は稲作技術とともに大陸からやってきたと考えられるのだそうです。


おっさんの孤立無援的紀行



「ゲテ食」大全

ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら(一部写真が載ってます。)
September 19, 2008 TIMESONLINE
オーストラリアでも最も人が訪れるサンゴ礁で何百種もの新種の生物が発見されたそうです。
今回の調査は Census of Marine Life(海洋生物のセンサス) に参加した科学者によって行われました。数多くの生物達が研究ステーションのすぐ近くにいる科学者やダイバー、グレートバリアリーフのプロのガイドの隣を泳いでいたわけですが誰もこれまでその重要性を認識していなかったのです。
新種が確認されたのはノースウェスト沖の Ningaloo Reef(ニンガルーリーフ) とノースイースト沖の Lizard islands(リザード島)、Heron is-
lands(ヘロン島) 沖で、リーフとは反対側を調査している時でした。
今回の調査は isopods(フナムシの類) やソフト・コーラル、ワームなどほとんど同定がされていない生物を中心に行われました。魚やハードコーラル、サメ、ウミウシといった生物についてはすでにまとめられているため省かれました。
「印象的だったのはこれほどの数の種類が目の前にいたことです。このあたりの場所は何年もの間人々がダイビングし研究ステーションも設置していたのです。」と Australian Institute of Marine Science(オーストラリア海洋科学研究所) の Julian Caley 氏は語っています。
彼は3回の調査で見つかったおよそ1000種類以上の生物のうち300から500は新種であると考えています。そしてまたさらにあと2年間の調査で更なる発見があるだろうと期待しているといいます。
これから詳細な分析は必要ですが、新種と考えられるのはソフト・コーラル150種、甲殻類130種、ワーム100種類ほどだといいます。新種のウニ、basket stars(テズルモズル)、海草でも新たな発見がありました。
今回発見された新種の中で特に研究チームの興味を惹いたものはフナムシの仲間だそうです。この生物は体長わずか数ミリしかなく、貴重な多様性のインジケーターであると考えられるからです。また彼らはこの生物の生きた魚の舌を食べるという不思議な生態を確認したいとも考えているようです。
同センサスのチーフ・サイエンティストである Ron O’Dor 氏は「リーフに住む驚くほどカラフルなサンゴや魚に長い間ダイバー達は目を奪われてきましたが、今回の調査でこの場所にはそれ以外にも実にたくさんの生物が暮らしていることに気づかされました。」と語っています。
海洋生物センサスは80カ国以上の国の科学者が参加するネットワークで今回の調査は4年にわたる研究プロジェクトの一環です。その目的は研究者が海洋環境の変化が及ぼす影響をより良く知ることができるように海洋生物について調査し幅広い基本的情報を提供することとのこと。
◆◇◆
海の生態系というのはそれほど幅広いということなのでしょうね。(海だけじゃないのかもしれませんが。)今回注目されているのはフナムシの仲間でタン・バイターとも言うべき寄生生物だそうで、生きた魚の舌を食べてしまい自分でその魚の口に取り付いて新たな舌になってしまうという摩訶不思議な生物とのこと。
新種とは関係ありませんが興味深いニュースを見つけました。なんでも弥生人はコイを飼って食料にしていた可能性があることが分かったそうです。滋賀県立琵琶湖博物館が愛知県の弥生時代中期の「朝日遺跡」を調査したところ、コイの幼魚と成魚の咽頭歯がみつかったとのこと。同博物館では幼魚を大量に捕獲するのは難しいため集落の環濠や水路などで養殖していたのではないかとみているそうです。古代中国ではコイの養殖方法を記した文献が見つかっているためこの技術は稲作技術とともに大陸からやってきたと考えられるのだそうです。

おっさんの孤立無援的紀行

「ゲテ食」大全
Posted by うおみ at 15:08│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。