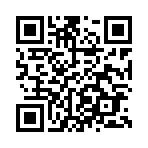2008年09月26日
うなぎのぼりに増える外来魚の話
こんなニュース見つけちゃいました。
ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
September 24, 2008 New Jersey News
アメリカ・ニュージャージー州では外来種 Asian swamp eel(タウナギ) の進出に頭を悩ませているそうです。
ヘビのような形をしたこの生き物は性を変える事ができます。繁殖するには好都合であり、その上肉食魚であるため周囲の水生生物を食べつくしてしまうのです。乾季には泥に潜ってエサなしでも数週間過ごすことが可能です。また陸上を歩くこともできより住みやすい環境を求めて移動することもあるといいます。
Division of Fish and Wildlife(ニュージャージー州魚類野生動物局) の主任水産生物学者 Chris Smith 氏は先週同州 Camden County(カムデン郡) の水路で何十匹ものタウナギを捕獲します。
今年になって Gibbsboro(ギブスボロ) の Silver Lake(シルバー・レイク) 周辺ではこの侵略者が数多く這い回り繁殖しているのが発見されたのです。ニュージャージー州では初めての目撃情報でしたが、すでに4つの州でこの生物の生存が確認されています。
Smith 氏はこれはウナギをペットとして飼育していた人が少なくとも4年前に水路に捨てた結果だと確信しているといいます。Smith 氏と彼の同僚は湖の周囲を歩きまわりタウナギを捕獲します。電気を発生する突き棒を使いウナギにショックを与え巣穴から飛び出させて網ですくい取るのです。小さいものはミミズほどですが、60センチ以上になるものもいます。
心配されるのはこの魚が在来種を食べつくして絶滅させある日気づいてみたらのっとられていたという事態です。タウナギは無脊椎動物から魚、爬虫類、両生類までなんでも食べるといいます。また天敵もおらず水の中でも外でもエサをとることができ、淡水でも濁った水でも大丈夫。さらに干上がった池や沼でも生き残ることができるのです。
外来種が生息する場合、在来の野生種に及ぼす影響は大きいものがあると彼は語ります。「どんな影響があるのか今のところ不明ですが、影響がでる前に駆逐したいと考えている。」と語ります。
州当局としては今のところタウナギの拡大状況を詳細に調査しているわけではないそうですが、下流の Cooper River(クーパー川) や Dela-
ware River(デラウェア川) 支流への進出は食い止めたいと考えているとのこと。
◆◇◆
このウナギはおよそ100年前にハワイで食料として飼育されていたものが逃げ出したと考えられ、1994年にはジョージアの池で、97年にはフロリダで生息が確認されているそうです。生物学者はハワイとフロリダの場合は食用のものが逃げ出したと考えていますが、ジョージアとニュージャージーの場合は素人の飼育者が捨てたものではないかと考えているそうです。
ウナギとは関係ありませんが感慨深いニュースを見つけました。トキが再び日本の大空を飛んだという話です。03年国内産の最後のトキ「キン」が死に野生のトキは絶滅しましたが、中国産のペアを飼育し人工孵化に成功。今では122羽にまで増えたそうです。今回そのうち10羽を佐渡の水田地帯に試験放鳥し野生復帰させるという試みです。10羽には個体識別用の足輪がつけられ、1部には GPS の送信機も取り付け今後も専門家らが行動調査を続けるとのこと。


うなぎを増やす



外来生物のリスク管理と有効利用

ニュースの概要だけ紹介しています。詳しい話はこちら
September 24, 2008 New Jersey News
アメリカ・ニュージャージー州では外来種 Asian swamp eel(タウナギ) の進出に頭を悩ませているそうです。
ヘビのような形をしたこの生き物は性を変える事ができます。繁殖するには好都合であり、その上肉食魚であるため周囲の水生生物を食べつくしてしまうのです。乾季には泥に潜ってエサなしでも数週間過ごすことが可能です。また陸上を歩くこともできより住みやすい環境を求めて移動することもあるといいます。
Division of Fish and Wildlife(ニュージャージー州魚類野生動物局) の主任水産生物学者 Chris Smith 氏は先週同州 Camden County(カムデン郡) の水路で何十匹ものタウナギを捕獲します。
今年になって Gibbsboro(ギブスボロ) の Silver Lake(シルバー・レイク) 周辺ではこの侵略者が数多く這い回り繁殖しているのが発見されたのです。ニュージャージー州では初めての目撃情報でしたが、すでに4つの州でこの生物の生存が確認されています。
Smith 氏はこれはウナギをペットとして飼育していた人が少なくとも4年前に水路に捨てた結果だと確信しているといいます。Smith 氏と彼の同僚は湖の周囲を歩きまわりタウナギを捕獲します。電気を発生する突き棒を使いウナギにショックを与え巣穴から飛び出させて網ですくい取るのです。小さいものはミミズほどですが、60センチ以上になるものもいます。
心配されるのはこの魚が在来種を食べつくして絶滅させある日気づいてみたらのっとられていたという事態です。タウナギは無脊椎動物から魚、爬虫類、両生類までなんでも食べるといいます。また天敵もおらず水の中でも外でもエサをとることができ、淡水でも濁った水でも大丈夫。さらに干上がった池や沼でも生き残ることができるのです。
外来種が生息する場合、在来の野生種に及ぼす影響は大きいものがあると彼は語ります。「どんな影響があるのか今のところ不明ですが、影響がでる前に駆逐したいと考えている。」と語ります。
州当局としては今のところタウナギの拡大状況を詳細に調査しているわけではないそうですが、下流の Cooper River(クーパー川) や Dela-
ware River(デラウェア川) 支流への進出は食い止めたいと考えているとのこと。
◆◇◆
このウナギはおよそ100年前にハワイで食料として飼育されていたものが逃げ出したと考えられ、1994年にはジョージアの池で、97年にはフロリダで生息が確認されているそうです。生物学者はハワイとフロリダの場合は食用のものが逃げ出したと考えていますが、ジョージアとニュージャージーの場合は素人の飼育者が捨てたものではないかと考えているそうです。
ウナギとは関係ありませんが感慨深いニュースを見つけました。トキが再び日本の大空を飛んだという話です。03年国内産の最後のトキ「キン」が死に野生のトキは絶滅しましたが、中国産のペアを飼育し人工孵化に成功。今では122羽にまで増えたそうです。今回そのうち10羽を佐渡の水田地帯に試験放鳥し野生復帰させるという試みです。10羽には個体識別用の足輪がつけられ、1部には GPS の送信機も取り付け今後も専門家らが行動調査を続けるとのこと。

うなぎを増やす

外来生物のリスク管理と有効利用
Posted by うおみ at 14:24│Comments(0)
│お魚ニュース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。